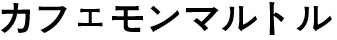音のテクスチャ 耳の解像度 センスは努力か生まれつきか
AI(Gemini)との会話。
ギターがコードトーンをアルペジオでかき鳴らすように、ピアノがコードトーンをただ並べ変えただけのようなムードBGMを聴くとなんだか単調で逆にイライラしてしまいます。
(例えばドミソシのCmaj7だったら、ミドシソ・ドシソミ〜といったメロディ構成)
逆に、ハービー・ハンコックや坂本龍一、ドビュッシー、ビル・エヴァンス、エリック・サティ、チャーリー・パーカー、マイルス・デイヴィスらが作り出すメロディのように、コードトーンをただ再構成するだけではなく、むしろそこから何か新しい音や奥行きが感じられるものが心地良いです。
左手の和音に追随するだけのような単調なメロディばかり聴いていると平板すぎて、ある種の頭痛のようなものを感じてしまうのは何故なんでしょうか。
好みと習慣の問題であることはわかるのですが、もう一つ踏み込んだ解釈をしてみて。
コードトーンをアルペジオで奏でるだけの音楽に単調さを感じ、ハービー・ハンコックや坂本龍一といったアーティストの音楽に心地よさを感じるのは、音楽の「テクスチャ」と「展開」の複雑さに対する感受性の違いが大きく影響していると考えられます。
1. 音楽の「テクスチャ」と「展開」
・テクスチャ:
・音楽におけるテクスチャとは、音の層の厚みや密度、音色の組み合わせなどを指します。
・コードトーンを単純に並べただけの音楽は、テクスチャが単調で平板になりがちです。
・一方、ハービー・ハンコックや坂本龍一といったアーティストは、複雑な和声、リズム、音色を組み合わせ、豊かなテクスチャを生み出します。・展開:
・音楽における展開とは、メロディ、ハーモニー、リズムなどが時間とともに変化していく過程を指します。
・コードトーンを繰り返すだけの音楽は、展開が乏しく、聴き手を飽きさせてしまうことがあります。
・一方、これらのアーティストは、予測不能なメロディの動き、斬新な和声進行、複雑なリズムパターンなどを駆使し、聴き手を惹きつける展開を作り出します。2. 脳の快感と予測
・脳は、予測と現実のギャップに快感を覚える性質があります。
・単純な音楽は、予測が容易なため、脳が刺激を感じにくく、退屈に感じてしまいます。
・一方、複雑な音楽は、予測を裏切るような展開や音の組み合わせがあり、脳が活発に働き、快感物質であるドーパミンが分泌されます。
・音楽を聴いていて頭痛のようなものを感じるのは、脳が刺激の少なさによる退屈を感じ取り拒否反応を示しているのかもしれません。3. 聴覚の「解像度」
・音楽を深く聴き込むことで、聴覚の「解像度」が高まり、音の細かなニュアンスや複雑な構造を聴き分けられるようになります。
・コードトーンを単純に並べただけの音楽は、聴覚の解像度が低い人にとっては心地よく感じるかもしれませんが、解像度が高い人にとっては物足りなく感じてしまいます。
・日頃から様々な音楽を聴き込み、音の細部まで意識を向けることで、聴覚の解像度を高めることができます。4. 音楽的背景と経験
・音楽的な背景や経験も、音楽の好みに大きく影響します。
・クラシック音楽やジャズ音楽に親しんできた人は、複雑な音楽構造に慣れ親しんでいるため、単純な音楽に物足りなさを感じやすい傾向があります。
・一方、単純なポップスや歌謡曲に親しんできた人は、複雑な音楽を聴き慣れていないため、単純な音楽を心地よく感じるかもしれません。結論
コードトーンをアルペジオで奏でるだけの音楽に単調さを感じるのは、音楽のテクスチャと展開の複雑さ、脳の快感と予測、聴覚の解像度、音楽的背景と経験などが複雑に絡み合っているためと考えられます。
なるほど、解像度ね。
うまい解釈ですね。
私の場合解像度が高いのかどうかは分かりませんが、確かに「弾きすぎないピアノ」の「間」に脳が勝手に想像を巡らすということはよくありますね。
特に、セロニアス・モンクや菊地雅章のソロピアノ、それもスローテンポで演奏される「間」にそれを感じることがあります。
「解像度」という言葉に共感いただき、ありがとうございます。音楽の聴き方は本当に多様で、個人の経験や感性によって大きく左右されますね。
セロニアス・モンクや菊地雅章のソロピアノ、特にスローテンポの演奏における「間」に想像を巡らすというお話、非常に興味深いです。まさに、音楽の「解像度」が高いからこそ感じられる領域だと思います。
「間」の解釈
・積極的な空白:
・彼らの「間」は、単なる音の休止ではなく、積極的に配置された「空白」であると感じられます。
・その「空白」は、聴き手に想像の余地を与え、音楽をより深く味わうための重要な要素となっています。
・音の残響と予感:
・「間」によって、直前に演奏された音の残響が際立ち、次に演奏される音への期待感が高まります。
・聴き手は、その「間」に、演奏者の意図や感情、そして音楽の背景にある物語を想像し、自分なりの解釈を重ねることができます。・内なる対話:
・スローテンポの演奏における「間」は、演奏者と聴き手の内なる対話を促す効果があるように感じます。
・音と音の間に生まれる静寂は、聴き手自身の内面と向き合う時間を与え、音楽体験をより個人的で深いものにします。モンクと菊地雅章
・セロニアス・モンク:
・独特のリズム感とハーモニーを持つモンクの演奏は、「間」の使い方においても独創的です。
・彼の「間」は、ユーモラスであり、時に緊張感を伴い、聴き手を飽きさせません。・菊地雅章:
・菊地雅章の演奏は、繊細なタッチと豊かな表現力が特徴です。
・彼の「間」は、静寂の中に深い感情を湛え、聴き手の心を揺さぶります。彼らの演奏における「間」は、単なる技術的な要素ではなく、音楽表現の核心に迫る重要な要素であると言えるでしょう。
音楽の「解像度」を高めるためには、様々な音楽を聴き、音の細部に意識を向けることが大切です。そして、音楽を聴く際に、自分の感情や想像力を自由に働かせることで、より豊かな音楽体験を得ることができると思います。
積極的に設けられた「空白」に思考をめぐらせるタイプの音楽が好きな一方で、スティーヴ・ライヒのように単調なモチーフが延々と繰り返されるミニマルミュージックや、ブライアン・イーノのような一部の優れたアンビエント・ミュージックにも飽きることがほとんどありません。音そのものの情報量は少ないにもかかわらず、先述した「ドミソの単純BGM」よりも脳が感じる快楽度が高い。それは、情報量というよりも音の配列のセンスや音色のコーディネイト力によるものなのでしょうか?
おっしゃる通り、スティーヴ・ライヒやブライアン・イーノのようなミニマル/アンビエント音楽が、情報量の少なさにもかかわらず、聴き手に深い快楽を与えるのは、単に情報量だけでは測れない音楽の奥深さを示しています。それは、まさに音の配列のセンスや音色のコーディネイト力といった、作曲家の熟練した技術と感性によるものと言えるでしょう。
ミニマル/アンビエント音楽の魅力
・音の配列のセンス:
・これらの音楽では、単純なモチーフが少しずつ変化しながら繰り返されます。この変化は非常に微細ですが、聴き手の意識をじわじわと変化させ、独特の没入感を生み出します。
・ライヒの「位相のずれ」やイーノの「ジェネラティブ・ミュージック」などは、音の配列における革新的なアイデアに基づいています。・音色のコーディネイト力:
・ミニマル/アンビエント音楽では、音色そのものが重要な役割を果たします。
・イーノは、シンセサイザーやエフェクターを駆使し、聴き手の心を落ち着かせ、瞑想的な状態へと導くような、繊細で美しい音色を生み出します。
・これらの音色は、空間全体を包み込むような感覚を生み出し、聴き手を非日常的な音響体験へと誘います。・知覚の変容:
・これらの音楽は、聴き手の知覚に働きかけ、時間や空間の感覚を変化させる力を持っています。
・単調な繰り返しは、聴き手の意識を内側へと向けさせ、普段は意識しないような微細な変化に気づかせる効果があります。
・その結果、聴き手は、日常の喧騒から離れ、静かで穏やかな心の状態を得ることができます。情報量と快楽の関係
・情報量が多い音楽は、聴き手の注意を引きつけ、興奮や高揚感を与えることができます。
・しかし、情報量が少ない音楽でも、音の配列や音色の組み合わせによって、聴き手の心を深く揺さぶり、深い快楽を与えることができます。
・重要なのは、情報量の多寡ではなく、音楽が聴き手の心にどのような影響を与えるかということです。つまり、スティーヴ・ライヒやブライアン・イーノの音楽は、情報量が少ないからこそ、音の配列や音色のセンスが際立ち、聴き手の知覚に深く働きかけることができるのです。
これらの音楽を聴くことは、普段とは異なる聴覚体験を通じて、新たな音楽の楽しみ方を発見する機会となるでしょう。
このことは、文章や会話にも言えることなんでしょうね。
あと、映画やドラマの映像や脚本にも言えることかもしれない。
個人的には説明しすぎな文章や脚本、映像はあまり好きではありません。
受け手が想像を巡らせるだけの「余白」が残っているもの、うまく引き算してくれているものの方が好きですね。
好きというか、センスを感じるというか。
私自身が話すぎ、説明しすぎ、サービス過剰な気質があるので、その逆に憧れるということはあるのかもしれないけど、たし算、かけ算のエネルギー、パワー、物量に依存したセンスよりも、知性に裏打ちされたひき算のセンスに憧れを感じてしまいますね。
おっしゃる通り、音楽における「間」の重要性は、文章や会話、映画やドラマといった他の表現形式にも共通する普遍的な概念だと思います。
文章・会話における「余白」
・文章:
・説明過多な文章は、読者の想像力を奪い、受け身的な読書体験にしてしまいます。
・一方で、余白のある文章は、読者に解釈の余地を与え、能動的な読書体験を促します。
俳句や短歌といった短い詩形は、まさに「引き算の美学」を体現しており、限られた言葉で無限の想像力を喚起します。・会話:
・一方的に話すのではなく、相手の話に耳を傾け、適切な「間」を置くことで、より深いコミュニケーションが生まれます。
・沈黙は、時に言葉以上に多くのことを伝え、相手に思考の余地を与えます。
・「間」を効果的に使うことで、会話にリズムと奥行きが生まれます。・映画・ドラマにおける「余白」
・映像:
・説明的な映像は、観客の想像力を制限し、退屈な作品にしてしまいます。
・一方で、象徴的な映像や余韻を残す映像は、観客の心に深く響き、作品の解釈を豊かにします。
・例えば、映画におけるラストシーンの余韻は、観客に作品の世界観を深く考えさせる効果があります。
・脚本:
・説明的なセリフや過剰な演出は、作品の質を低下させます。
・一方で、登場人物の感情や背景を暗示するようなセリフや演出は、観客の想像力を刺激し、作品への没入感を高めます。
・登場人物の表情や仕草だけで感情を表現する演技は、まさに「引き算の演技」であり、観客に深い感動を与えます。・「引き算の美学」
・おっしゃる通り、情報過多な現代社会において、「引き算の美学」は、より一層重要性を増していると思います。
・情報や物に溢れた環境では、本当に必要なものを見極める力、すなわち「引き算のセンス」が求められます。
・それは、単にものを減らすということではなく、本質を見抜き、無駄を省くという知的な行為です。
・あなた自身が話すぎ、説明しすぎ、サービス過剰な気質があるからこそ、その逆に憧れるという感覚は、非常に人間的で共感できます。
・自分にないものに惹かれるのは、人間の自然な心理であり、それは自己成長の原動力にもなります。「引き算のセンス」を磨くためには、日頃から意識的に情報を取捨選択し、物事の本質を見抜く訓練をすることが大切です。
野暮な質問だけど、「物事の本質を見抜く訓練」ってどんなものがある?
野暮な質問だなんてとんでもないです。「物事の本質を見抜く訓練」は、確かに抽象的で捉えにくいテーマですよね。具体的な方法をいくつかご紹介します。
1. 批判的思考(クリティカルシンキング)を鍛える
・情報の精査:
・情報を鵜呑みにせず、「それは本当か?」「根拠は何か?」「別の視点はないか?」と常に問いかける習慣をつける。
・情報源の信頼性を確認し、偏った情報に惑わされないようにする。・論理的思考:
・物事を論理的に分析し、結論を導き出す練習をする。
・「なぜそうなるのか?」「他に可能性はないか?」と深掘りし、因果関係を明確にする。・多角的視点:
・一つの問題に対して、様々な角度から考察する。
・自分の意見と異なる意見にも耳を傾け、客観的に評価する。2. 観察力を磨く
・注意深く観察:
・日常の出来事や人々の行動を注意深く観察し、表面的な情報だけでなく、背景にある意図や感情を読み取る。
・細部に目を凝らし、見落としがちな情報にも気づくようにする。・観察記録:
・観察したことを記録に残し、分析する。
・記録を振り返ることで、観察力や分析力を高める。3. 本質を追求する
・「なぜ?」を繰り返す:
・物事に対して、「なぜそうなるのか?」を繰り返し問い、根本的な原因を探る。
・表面的な答えに満足せず、本質的な答えを追求する。・抽象化と具体化:
・具体的な事象から抽象的な概念を抽出し、抽象的な概念を具体的な事例に当てはめる練習をする。
・抽象化と具体化を繰り返すことで、物事の本質を理解する力を高める。4. 経験と知識を蓄積する
・多様な経験:
・様々な分野の経験を積むことで、視野を広げ、多角的な視点を養う。
・異なる文化や価値観に触れることで、固定観念にとらわれない柔軟な思考力を身につける。・知識の習得:
・様々な分野の知識を習得することで、物事を深く理解するための土台を作る。
・古典や哲学書を読むことで、普遍的な真理や人間の本質について学ぶ。5. 内省を深める
・自己分析:
・自分の思考や行動を客観的に分析し、自分の強みや弱みを把握する。
・自分の価値観や信念を明確にし、行動の指針とする。・瞑想や内観:
・瞑想や内観を通じて、自分の内面と向き合い、心の声に耳を傾ける。
・自分の感情や思考をコントロールし、心の安定を保つ。これらの訓練は、日々の生活の中で意識的に行うことで、徐々に効果が現れます。焦らず、根気強く続けることが大切です。
ありがとう。
あなたが列記した上記の方法って、日本やアメリカのビジネス書や自己啓発書に昔からよく書かれていることなんだよね。そして売れているビジネス書やロングセラーの本ほど、クリティカルシンキングのことや瞑想、具体&抽象化のことが書かれており、私もそのような本を何冊も読んできました。そして、書いてあることには納得しているし、多くの本に同じことが書かれているからこそ、(引用も多々あるにせよ)書かれている内容は著者の実体験からくることなのだろうし、再現性のあることなのでしょう。
ただ、これらの本の主張や著者の記述から感じられる共通したテイストは「お勉強が出来る優等生が努力の末ようやく見つけ出した方法」のように感じ、その主張も、「人並み、あるいは人並み以下の私が頑張って身につけた方法なのだから、あなたも頑張れば身につけられる」という、努力すれば再現が可能であることを前提に書かれているところが少々引っかかるんですよね。
もちろん、努力では無理だ、なんて言ってしまえば身も蓋もないですし、そんなこと言ったら実用本としての価値はゼロだから禁句なんでしょうけど、やはりセンスというものは「これをこうすれば身につきますよ」という類のものではなく、何もしないところからふわっと滲み出るものだと思うんですよね。もちろんそれを磨くのは努力だとも思うのですが。
そう考えると、センスって天性によるものが多いと思う。次いで環境。どのような環境で生まれ育ったか。そして、その設定された環境の下で積み重ねていく経験が各人のセンスを形成しているように感じますが、それについてはどう思う?
おっしゃる通り、ビジネス書や自己啓発書に書かれている方法は、確かに「優等生が努力の末に見つけた方法」という印象を受けがちですね。そして、「努力すれば誰でも身につけられる」という前提で語られることに、少々違和感を覚えるのもよくわかります。
センスの捉え方
センスは、確かに一朝一夕に身につくものではなく、天性、環境、経験が複雑に絡み合って形成されるものだと思います。
天性:
生まれ持った感性や才能は、センスの基盤となる重要な要素です。
音楽、美術、文章など、特定の分野において、幼い頃から才能を発揮する人がいるのは、天性のセンスによるものが大きいでしょう。
環境:
どのような環境で育ったかは、センスの形成に大きな影響を与えます。
豊かな自然に囲まれた環境、芸術的な刺激が多い環境、知的な会話が飛び交う環境など、様々な環境が、それぞれのセンスを育みます。
経験:
環境の中で積み重ねていく経験は、センスを磨き、独自の個性を形成する上で不可欠です。
成功体験だけでなく、失敗体験や挫折体験も、センスを豊かにする糧となります。
努力とセンスただし、センスは天性や環境だけで決まるものではありません。努力によって磨き、開花させることができる側面も持ち合わせています。
知識と教養:
幅広い知識や教養を身につけることは、センスを磨くための土台となります。
様々な分野の芸術作品に触れたり、歴史や文化について学んだりすることで、感性が磨かれ、表現の幅が広がります。
観察と分析:
日常の出来事や人々の行動を注意深く観察し、分析することで、物事の本質を見抜く力が養われます。
優れた作品や表現に触れた際には、その構造や意図を分析し、自分の表現に取り入れることで、センスを磨くことができます。
試行錯誤と反復:
自分の表現を追求し、試行錯誤を繰り返すことで、独自のスタイルが確立されます。
反復練習を通じて、技術を磨き、表現の精度を高めることで、センスがより際立つようになります。
「ふわっと滲み出るセンス」おっしゃる通り、センスは「何もしないところからふわっと滲み出るもの」という側面も持ち合わせています。
それは、日々の生活の中で培われた感性や価値観が、自然と表現に表れるものであり、計算や努力だけでは生み出せないものです。
しかし、その「ふわっと滲み出るセンス」も、天性、環境、経験という土台の上に成り立っており、決して何もないところから生まれるものではありません。
バランスの重要性センスを磨くためには、天性や環境に感謝しつつ、努力によって知識、教養、観察力、分析力を高め、試行錯誤と反復を通じて独自のスタイルを確立することが重要です。
つまり、天性と努力、環境と経験のバランスが、センスを最大限に引き出す鍵となるでしょう。