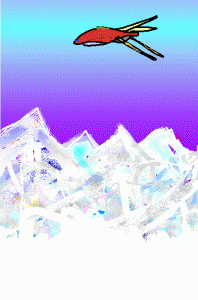超時空メルヘン「ババジ君」第2話
第1話からの続きです。
この事態を赤道上2000キロの上空からツブサに観察していた日本の軍事スパイ衛星、すめらのみことⅡ世号の乗り組員は、急いで出羽山脈の衛生管理システムの砦に急報を打ちました。
事態を重く見た局員はただちに日本国内にあるすべての秘密基地に光通信の暗号で、ことのあらましを通報しました。
数分後には瀬戸内海は明石にある東経135度観測基地の隊員であるユニワノイナホにも知る事となりました。
ちょうど、どんぐりで作ったパンを食べていた最中にこの知らせを受けたユニワノイナホは、何てこったと、どんぐりのパンが入っていた土器を床に落として割ってしまいました。
一つは、人間でありながら、音速を超える俊足を持つ子供の存在。
二つは、この倭(やまと)の国以外の場所で音速の7倍も出せる乗り物を開発できる技術力を持った国が存在したこと。
信じられないことではありますが、どうやら嘘でもないようです。
まずは、現場に行って自分のこの目で確かめてみることが先決です。
「隊長、天竺では何やら大変なことが起きているようです。私を現場に行かせてください。」
隊長も、同じことを考えていたようです。
「よし、ワシも同行しよう。」
かくして、明石東経135度観測所より、超音速ブースターロケットを装備した産土(うぶすな)号が発進することとなりました。
明石には、いわゆる高地性集落と呼ばれている地域がありましたが、実はこの砦の役割は戦争の時の要塞の役割はもちろん果たしましたが、それは表向きのこと、全長325メートルもの巨体の産土号の秘密基地でもあったのです。
産土号は巨大なナマズのような形をした乗り物なので、通常ですと空中に浮かび上がるための揚力を得るためには数キロもの滑走路が必要ですし、仮に離陸したとしても1万メートルの高々度にまで上昇するまでには、産土号搭載のターボジェットエンジンを使用すると、20分以上は優にかかってしまいます。
今回は非常時でもあるのでそんな悠長なことは言ってられません。緊急発進です。
真二つに割れた高地性集落の砦。中を覗くと300m以上もの深い穴、その中には、暗闇の中に赤々と無数の灯りがともり、まるで一つの巨大な都市の様相です。
ゆっくりとランチに乗った産土号が上昇してきます。地上に姿を現わすと同時にものすごい爆音とともに発進しました。
機首は地面に対してほぼ垂直、スペースシャトルの打ち上げ、あるいはサンダーバード1号が発進する様子に近いものがあります。
産土号に装着されたロケットブースターの燃料が尽きる頃、既に産土号の機体は高度1万2000mに達していました。
「隊長、そろそろ水平飛行にうつります。」
「いいだろう。」
産土号はロケットブースターを切り離すと水平飛行体勢にはいりました。
ものの10分の間の出来事です。
切り離されたブースターは当然地表に向かって自由落下をしますが、高度5000mのところで自動的にパラシュートが開き、瀬戸内海に着水、回収され再利用されるようになっています。
水平飛行状態の産土号は最高速度のマッハ5に加速し、一路、印度のデリーを目指しました。
絶えず衛星・すめらのみことⅡ世号から送られてくる誘導波を受信しながら自動航法装置に連動させているので、あとはゆっくりと操縦席でお茶でも飲んでいればいいわけです。
しかし、今回は事態が事態ですので、そんな悠長なことは言ってられません。
緊急会議です。
「ユニ、お前は今回の事態をどう捉えている?」
隊長はユニワノイナホに尋ねました。ユニワノイナホは、隊員たちからは「ユニ」と呼ばれているのです。
「隊長、私は思うのですが、あの子供は人間ではないと思うのですが。」
「というと?」
隊長は恐らくは顔の半分以上の面積を占めるであろう髭を撫でながら身を乗り出しました。
「人型のジェット兵器だと思うのですが。」
「ふむ、だとしたら事は重大だ。この産土号もマッハ5まで出すことはできるが、このように巨大な図体だ。また小型戦闘機の埴輪号も超音速航行は可能だが、やはりそれ相応の大きさだ。子供程度の大きさのメカに音速を超えるエンジンを搭載する技術なぞ、正直言って今の我々には無いぞ。」
隊長の眉間のシワがいっそう深くなります。ユニワノイナホの表情も一段と険しくなりました。
「隊長、攻撃力はどれくらいあるんでしょうかね。今のところ、相手に攻撃をしかけた形跡は認められませんが。」
「分からん、それも未知数だ。ただ超音速での敵の補足と追尾は、現状では外部ユニットに頼らざるを得ない。我々の赤外線自動追尾装置のようにな。もっともそれも我々の常識の範囲での話しだがね。」
「厄介なことになりましたね。これまで、亜細亜地域ではこのような兵器の存在は確認されていたのでしょうか?」
「いや、少なくとも“すめらのみこと班”からの報告は受けていない。今回我々が発見できたのも、もう片方の乗り物が爆発した際のおびただしい熱量を“すめらのみこと”Ⅱ世号が偶然補足したからに過ぎない。」
「もしかしたら我々の技術力の範疇では判断してはいけないことなのかもしれませんね。我々が用いている物体補足の手段は、もっぱら赤外線と電探(電波探知機=レーダー)の2点ですからね。」
「うむ、全ては現場を検証してからだ。」
産土号は現在高々度1万2000mの亜成層圏を飛行しています。
おおむね気流は安定していますが、時々激しい揺れがきます。ユニワノイナホがテーブルの上のコップ型土器に口をつけた瞬間、今まで一番激しい揺れが来ました。
ユニワノイナホは思わず土器を手放してしまい、床に叩きつけられた土器が鈍い音を立てて割れてしまいました。
「いっけねぇ、また割っちゃったよ。今日はこれで2度目だ。」
ユニワノイナホと隊長は操縦席にもどり、安全ベルトできつく体を固定しました。
ところ代わって、ここはデリーの街の郊外です。
デブヒゲ搭乗の「赤カブ号」が大爆発を起こしたころ、既にババジ君はデリーの街の郊外を全速力で駆け抜けていました。
つづく
⇒第3話
●index
第1話