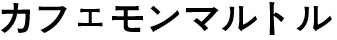雑想 2015年5月
2024/01/14
冷たく鋭い日本刀のようなコニッツ
これぞ「省略の美」というべきでしょう。
『コニッツ・ミーツ・マリガン』の《オール・ザ・シングズ・ユー・アー》は。
リー・コニッツのアルトが繰り出す鋭い出だし。
しかも、たったの2音。
この2音で、スタンダードナンバー《オール・ザ・シングズ・ユー・アー》の出だしのメロディに使用される数音を表現しきっちゃっている。
似たようなアプローチは、師匠のレニー・トリスターノと共演した『鬼才トリスターノ』でもしているけれど、ここでのプレイを、さらにキンキンに冷やして、鋭い刃物のように、研ぎに研いだ結果が、極限まで贅肉を落として引き締めた『コニッツ・ミーツ・マリガン』の演奏になっています。
アドリブも素晴らしいです。
何がって、「間」が。
ピアノレスの編成なんですが、コニッツが意図的に大きく「間」を設けている箇所がいくつかあるのですが、この「間」が、とても音楽しているんですよ。
ベースとドラムの躍動感がビシビシ伝わってくる。
そして、うっすらとマリガンの音も。
吹きすぎず、最小限の音で最大限の効果を狙う。
巧みな音配列。
素晴らしい集中力と、タイミング。
「最高」としか言いようがないコニッツのアドリブ、そして音色です。
クールどころか、コールド。
でも、音が出てくる情動、瞬発力は、超がつくほどホット。
聴こえてこないところが熱くて、聴こえてくるところは冷たい。
このギャップこそがコニッツの魅力なんです。
年齢を重ねるとともに、コニッツ特有のシャープさは、良い意味での丸さに変化していきますが、やっぱり私は、コニッツ若かりし日の冷たく鋭いまるで日本刀のようなコニッツのプレイが好きですね。
カール・パーキンス・トリオ
今年の連休期間中は、オーソドックスなピアノトリオを中心に聴いているような気がします。
普通のよく知られた曲を普通に演奏するからこそ、かえってピアニストの個性がハッキリと出てしまう。
料理人にオムレツのようなシンプルな料理を作らせると、その料理人の力量がわかってしまうのと同様、
ジャズの場合も、ピアノトリオのようなシンプルな編成で、オーソドックスなナンバーをオーソドックスに演奏するほうが、演奏者の腕やセンスが露わになってしまうので、かえって大変なことなのかもしれません。
その点、カール・パーキンスのピアノトリオは、安心して楽しめるオーソドックス名盤といえましょう。
初期のアート・ペッパーのバックでピアノを弾いている人でもあるので、耳に馴染みのある方も多いと思うのですが、アルト・サックスの脇役としてではなく、主役になったパーキンスのピアノもなかなかの力量です。
ハンプトン・ホースから、さらに湿気を抜いたような爽やかな演奏です。
音の粒立ち、輪郭がハッキリとしていて、カラッとしているんだけど、リロイ・ヴィネガー、ローレンス・マラブルという腰の据わったリズムセクションによって、きちんと粘りもたたえている演奏は、今の季節にピッタリなのではないかと思うのです。
▼収録曲
1. WAY CROSS TOWN
2. YOU DON’T KNOW WHAT LOVE IS
3. THE LADY IS A TRAMP
4. MARBLEHEAD
5. WOODYN YOU
6. WESTSIDE (AKA MIA)
7. JUST FRIENDS
8. IT COULD HAPPEN TO YOU
9. WHY DO I CARE
10. LILACS IN THE RAIN
11. CARL’S BLUES
12. WESTSIDE (AKA MIA) (ALT)
13. MEMORIES
記:2015/05/06
少年マイルスを救った先輩ディジーのアドバイス
マイルスは同じころ(パーカーにアドバイスをされた時期)、「あんたのように吹くにはどうすればいいんだ?」とガレスピーに訊いている。するとこんな返事が返ってきた。「できるさ、わたしが吹いている高音部中心のプレイを低音部に置き換えれば、お前のスタイルになるじゃないか」 この言葉がなかったら、少年の面影を残した18歳のトランペッターはさらに迷宮の奥深くへと入り込み、そこから脱出するのにもがき苦しんだかもしれない。(小川隆夫、平野啓一郎『マイルス・デイヴィスとは誰か』より)
少年マイルスを救った先輩パーカーのアドバイス
パーカーからの一言がマイルスの心に深く突き刺さった。「ひとの真似をするくらいなら、どうやったら自分の個性が表現できるかを考えろ。お前はスペースを生かしたフレージングにいいものがあるんだから、それに磨きをかけるべきだ」。間を生かしたフレージング。これこそがマイルスには神のお告げだった。ガレスピーのように吹きたくても吹けないもどかしさ。そのディレンマから救ってくれたのがパーカーの言葉だ。(小川隆夫、平野啓一郎『マイルス・デイヴィスとは誰か』より)
マゼラン星人マヤ ウルトラセブン
子どもの頃は、いちばん地味な回だと思っていたけれど、大人になると最も好きなエピソードになったのがウルトラセブンの「マゼラン星人マヤ」のエピソード。
絵作り、構成、構図、SE(バックのカツコツなど)、スタティックで退廃的な雰囲気などなど、すべて良いんだよね~。
「セブンの中では一番好きなエピソード」という特撮ファンも少なくないのでは?
コンプリート・レコーディングス エディ・コスタ
ピアニスト、ヴィブラフォン奏者のエディ・コスタは、32歳という若さで亡くなったため、わずか5枚のアルバムを残しているのみ。
彼が、生涯で残したたった2枚のトリオアルバム、『Eddie Costa With Vinnie Burke Trio(jubilee)』と、『The House Of Blue Lights(Dot)』がカップリングされた音源がコレ。
お得盤。
▼収録曲
1. Fascinating Rhythm
2. Unison Blues
3. Sweet And Lovely
4. Let's Do It
5. Yesterdays
6. Pile Driver
7. It Could Happen To You
8. Get Happy
9. Jeepers Creepers
10. The House Of Blue Lights
11. My Funny Valentine
12. Diane
13. Anabelle
14. When I Fall In Love
15. What's To Ya
日本人ジャズはスケールが小さい?
ジャズに限らず、映画にもその傾向は当てはまるかもしれないが、日本人の表現は、欧米のものに比べるとスケールが小さいとよく言われる。
あながち間違いではないと思う。
しかし、そのことをもってして、卑下することは的外れ。
ではアメリカ人が、日本人の表現のように小じんまりとまとまった表現が出来るのかというと、それは逆に難しいはず。
国や土地によって、そこで育った人々が育まれ、培われる感性の内容は異なるし、様々だ。
だから鑑賞者は自分好みのテイストを選べばいいだけの話。
日本のジャズのスケールが小さいと吹聴する暇があれば、スケールの大小では測れぬ、別な側面からの良さを見出す努力をすべきだし、それがイヤならば聴かねばよいのだ。
すべてのジャズが、あなたの好みにあわせて演奏してくれているというわけではないのだ。もしそう思っている人がいるのであれば、それは「思い上がり」だ。