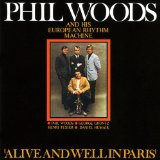アライヴ・アンド・ウェル・イン・パリ/フィル・ウッズ&ヨーロピアン・リズム・マシーン
メロドラマ?
うーん、クサい。
だって、一曲目のイントロなんか、もろ「メロドラマ」なんだもん(笑)。
切迫した声で「陽子さん!」「浩志さん!」「陽子さん、ぼ、ぼ、ぼ、ぼくは、あなたが…」なんて、一人芝居をやると、BGMとしては妙にハマッてしまうのだ。
まぁ、そんなアホなことをやているのは私だけかもしれないけど……。
しかし、この「メロドラマ」から一転、リズムが入り、少しずつ4ビートに変形してゆくあたりからは、既にフィル・ウッズとヨーロピアン・リズム・マシーンの演奏の虜となっている自分がいる。
殺人的なテクニックの持ち主
ウッズのタイトに引き締まったメタリックなアルト・サックスの音色。
このウッズのサックスを、ジャズ喫茶「メグ」のマスター・寺島靖国氏は「演奏だけ聴けば単なる機械だ」と評していたが、私はそうは思わない。
たしかに運指やタンギングは機械のように正確かもしれないが、「激情性」と「泣き」の要素は常にウッズのサックスには潜んでいる。これを聴き逃しちゃウッズの魅力はいつまでたっても分からない。
「泣き」といえば、そう、とくに、ベースソロが終わったあたりのウッズの激情的な「慟哭」。
びぎゃぁ~!!
たまりませんですね。
私の友人のアルト吹きに、熱烈なウッズ信奉者がいたが、その気持ちは分かるような気がする。
彼はウッズのサックスのことを「殺人的なテクニックの持ち主」と評していたが、サックスをやっている人がウッズに憧れるのは、ギター弾きが「早弾きギタリスト(笑)」に憧れるような気持ちに近いのかもしれない。
ロックを感じるストレートさ
正確なテクニックに加えて、ウッズの場合はすごく「ヒューマンな」肌触りが感じられる。
特に、このアルバムには顕著だが、「激情性」や「泣き」の要素。要所要所で叫んだり泣いたりしてくれるので、「分かりやすい」といっては失礼だが(決して「安易」という意味ではない)、聴いている者としては、気持ちを同化させやすいのだと思う。
「分かりやすいからロック」というのも安直な発想だが、ジャズを聴き始めたての頃の私は、ジャズ喫茶のスピーカーから大音量で流れてきたこのアルバムを聴いて、強くロックを感じてしまった(ちなみにその時はB面がかかっていた)。
ノリが良く、前へ前へと畳み掛けてくるリズムと、構成とメリハリのハッキリとしたウッズのサックス。
ストレートで一直線なのだ。
ジャズ特有のルーズなノリがその頃はイマイチ身体に染みこんでいなかった私にとっては、この直截的に斬り込んでくるサウンドは、ロックそのものに感じた(ちなみに、同時期に「ロック」を感じたもう一枚のアルバムは、マッコイの『サハラ』) 。
曲解説
さて、このアルバムについて少し。
この『アライブ・アンド・ウェル・イン・パリ』は、ウッズがヨーロッパへ渡って新たに結成したグループでの最初の吹き込みだ。代表作と言っても良い。
60年代に入ってからは、2枚しかアルバムの吹き込みがなかったウッズは、アメリカでは決して好調な活動状況とはいえなかったが、フランスへ移住し、心機一転。生き生きとした演奏で甦った。
冒頭で「クサいメロドラマ」と書いた曲は、《若かりし日(And When We Are Young)》。
「メロドラマ」というのは冗談で、これは、 ウッズと親しい間柄だったとされている、ロバート・ケネディへの追悼曲だ。
カリフォルニアで凶弾に倒れた上院議員のロバート・ケネディの死を悼んでウッズが作曲・演奏したもの。
オーバーなぐらいのセンチメンタルさは、そういった背景があったからなのだ。
「メロドラマ」だなんて不謹慎でしたね、失礼しました。
2曲目の《アライブ・アンド・ウェル》は、「俺は異国の地で、元気でやってるぜ!」といったウッズの言葉が聞こえてきそうな、勢いのある力強い演奏だ。
曲の一部にモード奏法が取り入られているが、モード奏法独特の響きに乗り、元気よく吹くウッズは躍動感に溢れている。
マイルス・デイヴィスも『マイルス・スマイルズ』で取りあげている有名曲、《フリーダム・ジャズ・ダンス》は、ひたすら格好いい。
マイルスの演奏よりもテンポが速く、勢いのある演奏だ。
ウッズが大好きな友人が最初に聴いたのはこの曲だったそうだが、一発でノックアウトされたという。分かるような気がする。
オリバー・ネルソンのちょっとノスタルジックで、幻想的な曲、《ストールン・モーメンツ》もかなりクサい演奏だ(すごく好きだけど)。
とくに、曲の肝とでも言うべき、テーマのラストの部分。小音量から次第にグロウをかけた大音量へフェイド・インしてゆく様は、演出過剰気味な気もするが、そこがまたクセになってしまう良さがあるのだ。
非ファンキーとしての《ドキシー》
ラストの《ドキシー》はソニー・ロリンズ作の名曲だが、これもかなり速いテンポで演奏されている。
競馬でも麻雀でも政治でも、あまりにも物事の本質を鋭く見抜いてしまい、歯に衣を着せぬ発言をしてしまうがゆえに、どっぷりと「その世界」に浸かっている「ユルくてヌルい人たち」からは、つねに反感とヒンシュクを買い、長い間一つの世界に止まることが出来ず、早々と自ら足を洗ってばかりの不幸な人・大橋巨泉が、ジャズ評論家だった時代に「ファンキー・ジャズ」を読み解く鍵は、《ドキシー》にこそあり、と評したほどの名曲だ(巨泉氏の論考は長くなるので割愛するが、私もその通りだと思うし、鋭い洞察だと思う)。
そんな《ドキシー》は、ちょっとかったるいくらいのゆったりしたテンポこそが最上だと思っている私にとっては、《ドキシー》の持ち味を破壊しかねないほどのハイ・テンポでスラスラと演奏されている。
しかし、演奏時間の短さもあり、「パワーアップしたボクの演奏はどうだった? 今日のところはコレでオシマイ。次も楽しみに待っていてね」といったような、エンディングの軽い挨拶のようにも聴こえるので、これはこれで悪くはないのかな、と最近は思うようになった。
矢野顕子の愛聴盤でもある
とにかく、フィル・ウッズは、テクニックもリズム感も抜群な上に、曲の聴かせるツボもよく心得ている人なので、とても聴きやすい上に、爽快な気分になれるサックスだと思う。
そういえば、昔、何かのインタビューか、雑誌か忘れてしまったが、矢野顕子が好きなジャズの一枚にこのアルバムを挙げていたことが妙に印象に残っている。
記:2002/04/08
album data
ALIVE AND WELL IN PARIS (Odeon)
- Phil Woods
1.And When We Are Young
2.Alive And Well
3.Freedom Jazz Dance
4.Stolen Momments
5.Doxy
Phil Woods (as)
George Gruntz (p)
Henri Texier (b)
Daniel Humair (ds)
1968/11/14 & 15