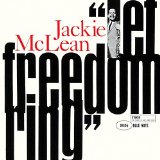レット・フリーダム・リング/ジャッキー・マクリーン
ジャッキー・マクリーンが、新しいジャズを模索したアルバム。
ハードバップ路線のマクリーンから心機一転、“彼なりに”新しい試みをしている意欲作でもある。
発売当初は、路線変更に怒ったファンに、街で殴られたというエピソードもあるが、モードやフリーに聴き慣れた現在の耳からすると、特に変わった内容とも思えず、ハードバップの延長線上のサウンドに聴こえる。
オーソドックス、つまり聴きやすい。
大きな変化を強いていえば、フリークトーン(フラジオ)を多用していることと、より長めの音符を吹き、パワフルさとアグレッシヴを強調した“歌い方”になっていることか。
曲中、意図的に(そう、自然発生的にではなく、意図的に)フリークトーンを混ぜることが、果たして彼の考える新しいジャズなのかどうか、また、新しいジャズの潮流に対しての彼なりの回答なのかどうかは大いに疑問だが、彼の表現の射程内にはオーネット・コールマンの存在が大きく横たわっていたことは想像に難くない。
アプローチ、そして出てくる音は、オーネット的ではなく、マクリーンそのものだが、彼なりに「周りには遅れないぞ。自分もなにか新しいことやらなくちゃ」という意識を抱かせ、突き動かしたのは、やはりオーネットの既成の価値観に拘泥しない自由奔放な表現だったのではないかと私は想像する。
加えて彼も同じアルト・サックス奏者だし。ライバル意識も、もしかしたらあったのかもしれない。
もっとも、そういう衝動に駆られ、新しい試みを模索したジャズマンはマクリーンだけではないので、当時はジャズマンたちの意識が既成のハードバップから少しでも脱却しようと働いていた時代だったのかもしれない。
たとえば、マクリーンの場合はフリークトーンを多用しているが、ロリンズの場合は、サックスからマウスピースをはずして「ピーピー」と笛のように吹いていた(『イースト・ブロードウエイ・ラン・ダウン』)。
時代の流れを、各々のジャズマンが受け止め、考え、模索し、彼らなりの回答をプレイをしていたのだろう。
必ずしも成果を結んだとは限らないかもしれないが、オーネット出現以降というのは、各々のミュージシャンは自分のスタイルについて考えることを余儀なくされたのだろうし、多くのジャズマンはチャレンジ意欲に溢れていた時代だったのだろう。
そんな時代的な雰囲気の中の産物が、この『レット・フリーダム・リング』だ。
アルバムの内容だが、一曲目の出だしを聴くと、私はいつもセロニアス・モンクの《ブリリアント・コーナーズ》を思い出してしまう。
メロディが似ているということが一番の理由だが、ピアノのイントロと、重心低めにはいってくるマクリーンのアルトの感じが《ブリリアント・コーナーズ》そのもの。
しかし、Bメロに突入したあとのロングトーンは、やはりマクリーンならではの“泣き”だ。緊張感のあるスタートなだけに、ここの部分はホッとする一瞬。
アドリブでは、例のフリークトーンが多用されているが、耳障りでは無いにせよ、ちょっとしつこい気もする。
この試みは、マクリーンにとっては新しいは新しいが、新しいだけで、アドリヴの中に何度も何度も繰り返されるだけの必然性は、あまり感じられない。
もっとも、これは聴き手の好き嫌いで大きく分かれるところなので、リスナー各人の判断に委ねるとしても、私はこれを聴くたびにマクリーンっていう人は基本的にはとっても真面目で律儀な人なんだなぁと思ってしまう。
というのも、フリーキーなトーンを出す場所があらかじめ決められているように感じられ、マクリーンのプレイからも「よし!次の瞬間に出すぞ」という空気が見え見えなのだ。
また「もっとフリークトーンを鳴らさなきゃ」という義務感のようなものまでも感じ取れてしまう。
「激情の赴くままに演奏していたら“結果的に”こういうフリークトーンの混ざった演奏になっていまいました」
ではなく、
「最初からフリークトーンを出すことを前提で曲に挑みました。」という感じなのだ。
あらかじめフリークトーンを出す上でのアタリを付けた上で演奏に臨んでいるように私には感じられるが、もし、本当にそうだとしたら、マイルスほど演出巧みでも器用でもない正直者なマクリーンゆえ、手の内が聴き手にすぐにバレてしまうところが、なんとも彼らしいし、そういうマクリーンだからこそ、私は彼に愛着を覚えるのだ。
二曲目の《アイル・キープ・ラヴィング・ユー》は、バド・パウエルの名曲。
この繊細で美しいバラードを、エモーショナルに、そして大胆にデフォルメした演奏は、好き嫌いが大きく分かれるところだろう。
私は嫌い。
ただし、パウエルの演奏は大好きだが。
マクリーンの《アイル・キープ・ラヴィング・ユー》を聴くと、ハワイで食べたステーキを思い出す。
大味すぎるのだ。
《レフト・アローン》のような繊細さが、あまり感じられないバラード表現。
しかし、大味でベタな表現を好む人も多いことも確か。
私は“大味”という表現を使っているが、言葉を返せば、“スケールの大きい演奏”なのかもしれず、むしろ、そう感じている人のほうが多いのかもしれない。
3曲目、4曲目も熱演。エキサイティング。
《ルネ》とは、息子に捧げた曲なのだろうか?
全体的には、新主流派的なテイストのサウンドのアルバムで、それぞれ演奏者の意気込みが伝わってはくるが、コンセプトの刷り合わせが徹底してないのだろうか、時折、ピアノのウォルター・デイヴィスが、スタンダードの一節を能天気に弾いてしまう箇所もある。
私はそういう徹底しきれていない「綻び」のようなところにこそ、親しみを感じる。
フリーク・トーンを除けば、親しみやすい、マクリーン流・新主流派アルバムといったところか。
album data
LET FREEDOM RING (Blue Note)
- Jackie McLean
1.Melody For Melonae
2.I'll Keep Loving You
3.Rene
4.Omega
Jackie McLean (as)
Walter Davis (p)
Herbie Lewis (b)
Billy Higgins (ds)
1962/03/19
記:2002/10/11