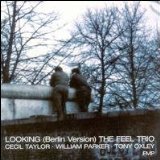ルッキング(ベルリン・ヴァージョン)ザ・フィール・トリオ/セシル・テイラー
凄まじい刺激と興奮
まさに「暴風雨」という形容がふさわしい。
特に《セカンド・パート》において、それが顕著だが、演奏が進むにつれてテイラーのピアノは加速してゆき、不気味なウネリを見せる。
テイラーのピアノは、山下洋輔的な、一直線にクライマックス突き進むタイプとは対極に位置し、蛇行と収縮・拡散を頻繁に繰り返しながら、イキそうでイカなかったり、あるいは、拍子抜けするほどあっけなくクライマックスに達したりと、良い意味で聴き手の期待を裏切る“一筋縄ではいかなさ”が大きな特徴だが、ここでの演奏は、比較的分かりやすい内容だといえる。
途中でいくつかの“谷”はあるにせよ、基本的には“前進”と“加速”の連続だ。
だからといって、決して単調な演奏というわけではない。
圧倒的な音数の中にも、細かなメリハリと目まぐるしいニュアンスの変化がキチンとつけられている。
テイラーのピアノを次第にエキサイティングに盛り上げてゆく“触媒”としてトニー・オクスレイの存在は大きい。
テイラーの繰り出す複雑な音塊に的確に反応し、瞬時に局面に変化をつけるだけの耳の良さと反応の良さを持つ素晴らしいパーカッショニストだと思う。
ベースのウイリアム・パーカーも負けてはいない。
彼の細かい不定形なビート、ではなく、“パルス”は、相当な修練の賜物だと、同じベース弾きとしては感じる。
テイラーの荒れ狂うピアノに対して、もし自分がベースで共演するとしたら、いったいどのようなアプローチを繰り出せば良いのか、色々と考えても全くイマジネーションの沸かない私だが、彼のベースワークがひとつの素晴らしい模範解答となっている。
一聴すると、適当に弾いているようにも感じるかもしれないが、演奏からベースが抜けたときの状態をイメージしてみると良いだろう。
ベースがあるのと無いのとでは、サウンドの立体感と陰影がまるで違ってくることに気がつくと思う。
まるで、テイラーの影のような存在として、テイラーのピアノに立体感と深みを与えているのだ。
何かの本かインタビューで読んだことがあるのだが、セシル・テイラーと共演するためには、3年はみっちりとトレーニングを重ねないことには難しいのだそうだ。
たしかに技量的なことはもちろんだが、長尺な演奏と、衰えを知らないパワーに振り落とされずについて行くためには、相当な精神的な強さも必要なのだろうと思う。
一年に何回も聴くような類のアルバムではないが、たまに思い出したように聴くと、凄まじい刺激と興奮を味わえる内容だ。
記:2003/11/13
album data
LOOKING (BELRIN VERSION) THE FEEL TRIO (FMP)
- Cecil Taylor
1.First Part
2.Second Part
3.Third Part
Cecil Taylor (p)
William Parker (b)
Tony Oxley (ds)
1989/11/02
Recorded Live By Holger Scheuermann And Gebers
at The Quartier Latin In Berlin