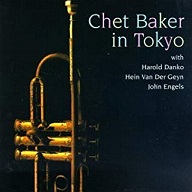チェット・ベイカー・イン・トーキョー/チェット・ベイカー
チェットの存在感
もうこの時期のチェットは、つまり晩年のベイカーは、何をどう歌おうが、チェット意外の何者でもない風情を纏っていた。
あとは、その日の調子が良いか悪いだけ。
良いコンディションのときは、本当に良い演奏をするし、それもあっといわせるようなインパクトのあるトランペットというよりは、心に染みてゆく深度の深い演奏をする。
調子が悪いときだって、なんだか耳をそばだてざるをえない「揺らぎ」を放ち、結局のところは最後まで聴いてしまう。
そう、結局は「聴けてしまう」。
なんて得なプレイヤーなんだ、というとヘンな言い方だが、結局何をどうしようが、チェット・ベイカーは、チェット・ベーカー発する音の存在感だけで聞かせてしまうのだから、それはそれで凄いことだ。
そして、奇をてらったり新しいアプローチをしなくても、つまりしゃかりきに頑張らなくても、自分を自然に出せてしまうこと、これって、究極のところ、どのミュージシャンもたどり着きたい境地なのではないだろうか?
1984年の来日時、昭和女子大学人見記念講堂で行われたコンサートは、すこぶる調子が良いベイカーを楽しむことが出来る。
編成はワンホーンカルテット。
チェットのトランペットと歌を存分に堪能できる編成だ。
ピアノのハロルド・ダンコのセンスあるサポート良し。
ベースのハイン・バン・ダー・ガインの低音も心地よく染み入り、時として聞いているときの気分が気持ちよくてダレてしまいそうなリスナーの耳をシャキッとさせてくれるジョン・エンゲルスのドラミングも良いカンフル剤だ。
ちなみにドラムスは当初、ベン・ライリーだったそうだが、何かの都合でジョン・エンゲルスに変わったようだ。
しかし、メンバーが変わったことによってバンドサウンドがどうのこうの、グループとしてのまとまり云々以前に、もうこの時期のチェット・ベイカーの音楽は、「チェットを含めたバンド全体」のサウンドよりも、「チェット+バックバンド」というような音楽になっている。
おそらく本人も、そしてメンバーたちも、そのような意識で演奏に臨んでいるのではないだろうか。
つまり、極論すれば、どんなにバックの演奏陣の演奏がヘボくても(このアルバムの演奏は素晴らしいが)、チェットのトランペットやヴォーカルが聴ければ、それはそれで良いのだという気分にさせてしまいそうなところが、やはりチェットのズルくてお得なところなんだと思う。
この時期のチェットは、努力もエネルギーもさほど費やさずとも、自然に人の心と耳を鷲づかみにしてしまう究極の境地にたどり着いてしまったのかもしれない。
記:2019/08/21
album data
CHET BAKER IN TOKYO ()
- Chet Baker
disc 1
1.Stella By Starlight
2.For Minors Only
3.Almost Blue
4.Portrait In Black And White
5.My Funny Valentine
disc 2
1.Four
2.Arborway
3.I'm A Fool To Want You
4.Seven Steps To Heaven
5.For All We Know
6.Broken Wing
Chet Baker (tp,vo)
Harold Danko (p)
Hein Van Der Geyn (b)
John Engels(ds)
1984/06/14
昭和女子大学人見記念講堂
YouTube
動画でもこのアルバムを紹介しています。