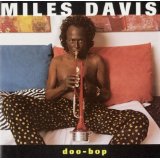ドゥー・バップ/マイルス・デイヴィス
ドゥー・バップ
これを聴くたびに意識が冷たく覚醒していく。
と同時に、マイルスの哀しげなミュートトランペットに同化していけばいくほど、やるせない気分になっていく。
これはたぶん、マイルスの肉声(=トランペットの音色)がリアルに何の抵抗もなく体内に侵入してくるからだろう。
打ち込みビートだからこそ、逆にマイルスのトランペットが生々しく浮き彫りになってくるのだ。
これがバンド形式だと、優秀なサイドマンたちがマイルスの音を敏感に聴き取り、瞬時に反応してくれるので、マイルスのトランペットを効果的に引き立てる役目は果たしてはくれるだろう。
しかし、バックのトラックがマイルスの音を聞く耳持たぬ「打ち込み」だと、何をどんな音色でどう吹こうが、オケはお構いなしに打ち込まれたプログラムを淡々と処理するのみ。マイルスの音に反応をすることはない。
もちろん、復帰後のマイルス・デイヴィスの作品にはマーカス・ミラープロデュースの『TUTU』を筆頭に、バックのトラックが打ち込みの曲は少なくない。
しかし、イージー・モービーが手掛けるヒップホップのトラックは、練り込まれたアレンジの対極ともいえるラフで単調な打ち込みパターンだ。
だからこそ、バックのトラックが簡素であればあるほど、トランペットのサウンドが引き立ち、マイルスが音に込めたニュアンスやアーティキュレーションが生々しいほどに浮かび上がってくるのだ。
たとえ、エコー(正確にはディレイ)がかかっていようとも。
いや、むしろ、エコーがかかっていたほうが「哀しみのトランペット」効果が倍加する不思議さがあり、それは『死刑台のエレベーター』においても、エコーがかかったトラックのほうが、よりマイルスらしいということと同じ現象なのかもしれない。
しょっぱなからエコーがかかったミュートトランペットからスタートする《ミステリー》。
このナンバーがアルバムの冒頭であることの意義は大きい。
出だしの過剰なほどのディレイが繰り返されるミュートトランペットの哀しい高音がこのアルバムの雰囲気を決定づけているといっても過言ではない。
リズムトラックが、いい具合にラフなパターンを反復してくれるがゆえに、より一層マイルスが放つ空気が耳の奥底まで侵入してくるのだ。
このラップが入らぬ《ミステリー》というインストナンバーを先頭に配してあるのは心憎い編集だと思う。まずは聴き手の気分をマイルス色に染め、気分が満ちてきたタイミングで次曲の《ドゥーバップ・ソング》に流れるという流れは、いつ聴いても完璧だと感じる。
ドゥーバップ・ソング
2曲目はラップ入りの《ドゥーバップ・ソング》。
ラップは、やけにマイルスを褒め称えている内容ではあるが、それを差し引いても、このアルバムのベストトラックだと思う。
何の違和感もなくマイルスのトランペットはバックのサウンドに溶け込んでいるところが素晴らしい。
物悲しく反復されるシンセの柔らかい和音が、鋭く哀しいミュートトランペットの音色を鮮やかに引き立てている。
やはりコード楽器は、マイルスのトランペットにおいては、ピアノのような硬質な音色よりも、アタックの弱いオルガン系やストリングス系の音色が相応しいのかもしれない。
もちろん、かつてマイルスのグループには素晴らしいピアニストが何人も在籍していたが、皆、バッキングに回ったときは弾き過ぎず邪魔をし過ぎず、影になりつつも効果的なピアノを弾くように意識していたのかもしれない。
甘い音色で柔らかなブロックコードを発するレッド・ガーランド。
音数少なく発する音の一音一音がリズミックなウイントン・ケリー。
ハーモニーもリズムも独自の美学を貫くビル・エヴァンス。
曲によってはマイルスがトランペットを吹いている間はまったくピアノを弾かないハービー・ハンコック……。
さらに時代を遡ると、マイルスは硬質な和音を弾くセロニアス・モンクに「自分がトランペットを吹いている間はピアノを弾かないで欲しい」と注文をつけ、ホレス・シルヴァーがマイルスのバックでピアノを奏でる際は、自身がリーダーの時の演奏の半分以下の音数だった。
むやみやたら「ただピアノを弾く」タイプのピアニストはマイルスのバンドに所属していなかったことを考えると、マイルスが求めるコード楽器像というのは、自身のトランペットを受け止める柔らかなクッションのようなニュアンスを欲していたのかもしれない。
特に鋭いミュートトランペットと、アタックの強いピアノの音ぶつかり合う可能性もあり、このことをマイルスはかなり初期の段階から懸念していたのではないか。
フレンチホルンなど、ジャズのビッグバンドではあまり使われることがない楽器を積極的に取り入れたアレンジャー、ギル・エヴァンスを生涯評価していたのも、ギルのハーモニー感覚はもとより、暖かく柔らかでスムースなサウンドをギルの手腕を買っていたからかもしれない。
そう考えると、エレクトリックピアノの出現で、ピアノからエレピにバンドのサウンドが移行していったのは分かるような気がする。
マイルスがコード楽器に求めていた柔らかくクッションのような、そして具体的過ぎず、何かを暗示するするような曖昧さを残した響き。
はからずとも、ジャズとはまったく畑違いのヒップホップのミュージシャンが知ってか知らずか、偶然か意図的か、マイルスサウンドにピタリと合致するサウンドを作った。
それが《ドゥーバップ・ソング》だと思う。
マイルスとヒップホップの親和性の高さ云々ではなく、また、マイルスがヒップホップ的な音楽表現に寄り添ったのでもなく、ヒップホップ畑の人たちが用意したトラックは、最初からマイルスにジャストフィットするサウンドだったのだ。
私はそう解釈しているし、だからこそ『ドゥ・バップ』ほどトランぺッター、マイルス・デイヴィスらしさを感じるアルバムもないとも感じている。
そんなことを考えながら『ドゥ・バップ』の《ザ・ドゥ・バップ・ソング》を聴いている今日この頃なのです。
記:2014/05/23
album data
Doo Bop (Warner)
- Miles Davis
1. Mystery
2. The Doo-Bop Song
3. Chocolate Chip
4. High Speed Chase
5. Blow
6. Sonya
7. Fantasy
8. Duke Booty Miles Davis
9. Mystery (Reprise)
Miles Davis (tp)
Easy Mo Bee (programing,sampling,rap#2,5,7)
J.R. (rap #2)
A.B.Money (rap #2)
Deron Johnson (key)
1991/1-2 New York