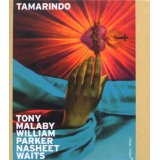タマリンド/トニー・マラビー
フロントとリズムのユニークな関係性
これを聴くたびに、水木しげるの絵を思い出す。
なんでもいい、水木しげるの妖怪事典(あるいは図鑑)をひも解いてみよう。
おそろしく緻密に描写された妖怪と背景。
それに対して、妖怪を見ておどろく人物、妖怪に出くわし、恐れおののく人物の描写はいたって簡素だ。
バックの風景は、板の木目から、葉っぱの葉脈、道端の石ころの陰影までもが、緻密なほどに細かく無数の点と線で描き込まれている。
反対に、人間の描写は、基本的には線とベタ塗りのみ。
このギャップが、まさに水木しげるならではの作風。
人物を描き込みすぎないことによって、絵としてのバランスを保ち、視線の“力の抜きどころ”をも提供しているかのようだ。
このギャップは、まさに今、ニューヨークのジャズシーンで注目を浴びているテナー奏者、トニー・マラビーがピアノレス・トリオで録音したリーダー作『タマリンド』のアンサンブルの位置関係を連想させるものがある。
つまり、妖怪を見て驚く人間がマラビーのテナーだとすると、偏執的にまで描きこまれた背景がベースとドラムのリズムセクション。
緻密で陰影に富み、時間を克明に描写するベースとドラムのリズムセクションに比べると、マラビーのテナーのフレージングは驚くほど簡素だ。
もちろん、シンプルだからといって、《セント・トーマス》や《テイク・ファイヴ》のメロディのように平易で、口ずさめるほどキャッチーな内容だというわけではない。
むしろ旋律がをシンプルなぶん抽象度が高まっているので、キャッチーさからはほど遠い。
マラビーのテナーは、たとえば、ジョン・コルトレーンのように時間を音符で塗りつぶすようなシーツ・オブ・サウンズとはまるで正反対の世界。
コルトレーンの時間感覚をより平面に、横へ横へと拡張したかのようなフレージングは、要するにロングトーンが多く、音数が少ない。
少ない音数のぶん、フラジオやグロウルをかけるなど音色に変化をもたらし、テナーの音色に様々な表情をつけることによって、一見豪快でいて、そのじつ緻密なニュアンスをもリスナーに印象づける。
水木しげるが描き出す人間は、その線の数の少なさから一見シンプルに見えて、そのじつ、線の太さや、ふるえるような曲線を随所に混ぜて微妙な変化をもたらしているが、まさにマラビーのテナーも同様。
ロングトーンのたった一音にも、微妙なニュアンスが込められている。
このシンプルさは、アルバート・アイラーの原始的咆哮とはまた違った、緻密に計算されたしたたかさとタフさが感じられ、バックのリズムセクションも、微妙な陰影に富んだマラビーのテナーに触発されて、さらにリズムの奥行きを増すという仕組み。
つまり、リズムセクションに鼓舞されてフロントのサックスが燃え上がるのではなく、むしろ、マラビーのサックスに鼓舞されてバックのリズムセクションが燃え上がるという構図に感じられる。
そういった意味では、マラビーのシンプルだが暗示的なテナーこそが、まさに演奏の触媒であり、推進力なのだ。
それにしても、ベースのウィリアム・パーカーといい、ドラムスのナシート・ウエイツといい、彼ら2人の黒人リズムセクションが編み出すリズムの強靭さと反応の俊敏さはどうだ。
あたかも鍛え抜かれたアスリートの名人芸に触れているような感覚を覚えるのは私だけではあるまい。
この『タマリンド』の聴きどころは、まさにフロントとリズムセクションの関係性、距離感にある。
もし、演奏のポイントが掴みづらければ、まずは骨太で曲の枠組みを築きあげているベース、ついでそれにシャープなスピード感とウネりを加えているドラムをひたすら追いかけてみることをオススメしたい。
理解のポイントはリズムセクションから。
そうすれば、自ずとマラビーのテナーの面白さにも開眼してゆけることだろう。
記:2009/07/22
album data
TAMARINDO (Clean Feed)
- Tony Malaby
1.Buried Head
2.Floral And Herbacious
3.La Mariposa
4.Tamarindo
5.Mother's Love
6.Floating Head
Tony Malaby (ts)
William Parker (b)
Nasheet Waits (ds)
2007年