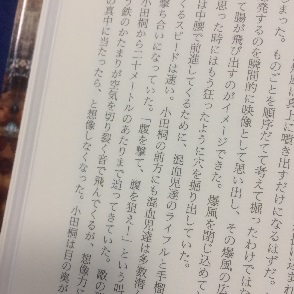グルーヴする村上龍の文体~『五分後の世界』と『愛と幻想のファシズム』
『五分後の世界』で文体研究
先日、久々に村上龍の『五分後の世界』を見た。
読んだ、のではなく、見た。
すでに20回以上再読している作品なので、もちろん要所要所好きなシーンの文字は「読んだ」のだが、どちらかというとページをめくりながらぼんやりと眺める感じ。
なぜそのようなことをするのかというと、大げさにいえば村上龍の文体研究かな?
村上龍という作家の文体は、時期や作品によってもかなり違うのだが、今回は私が大好きで20回以上も再読してしまっている『五分後の世界』が、なぜかくも読みやすいのか、胸をかきむしられるような不快な気分にもなることもありながらも、結局はカッコ良さが鳥肌もののラストまで一気に読み進めてしまえるのかを自分なりに分析してみたかったからだ。
独特な「、」の打ち方
読んだことがある人はわかると思うけれど、国連軍との戦闘シーンなど、まったく改行がないページもある。
特に戦闘シーンの箇所は、ページの隅から隅まで文字で埋め尽くされているところもあり、活字嫌いが見れば一瞬で白旗を掲げて降参してしまうほどの文字の密度だ。
それなのに、なぜかくも読みやすいのか。
もちろん、芥川賞作家ならではの圧倒的な筆力や、凄惨な戦闘シーンが有無を言わさず読み手の本能を揺さぶるということもあるだろう。
しかし、それだけなのだろうか。
私は句読点の「点(、)」の打ち方に秘密があるのではないかと思っている。
これに気が付いたのは、もうずいぶん昔のことで、『愛と幻想のファシズム』を読んでいるときだった。
鍵括弧で括られたセリフであるにもかかわらず、途中で改行されているところもあることに気が付いた私は、セリフの言葉を中心に読んでいくと、句読点の打ち方が独特なことに気が付いた。
本来なら「句点(。)」にすべきところを「読点(、)」を打つことで、独特なリズムを生み出しているのだ。
緊迫感といっても良い。
濃縮された情報が凄まじい速度で眼前に繰り広げられているかのような気分になる。
例えば、主人公・鈴原冬二のセリフだが、改行と「、」に注目してみよう。
「(前略)日本の金を返させるんだ、同じように、スイスの金も、ドイツの金も、イギリスの金も、返させる、
脅迫しなければ、絶対に連中は返そうとはしないだろう、脅迫の方法が大切なんだ、イスラエルから貰った金属プルトニウムで核兵器を作って、それで脅しても、大した効果はないし、国際世論から袋叩きにあう、
もし、飛駒が言ったことが実現できれば、それ以上の方法はないだろう、オレ達は、アメリカを叩く英雄とならなければいけないのだ、成功すれば、国内支配など目をつぶってでもやれる、
飛駒、お前、期限があるって言ってたな、どういうことなんだ?」
黄色いマーカーをつけた「、」のところは、普通は「。」を入れるよなと思われるところ。
「、」で終わって改行しているところもあるよね。
しかし、この冬二のセリフ、「、」のところを「。」にしてしまうと、緊迫感の温度が随分と変化してしまうのではないかと思うのだ。
物騒な話を落ち着いた口調で話しているように感じるかもしれない。
しかし、「。」で区切るところに「、」を用いることで、畳みかけるような緊迫感を生み出すことに成功しているのではないかと思うのだ。
情報量を圧縮する効果
そして、「、」という合いの手を文章の至るところに入れることで、それこそジャズドラマーのフィリー・ジョー・ジョーンズやルイス・ヘイズが途中で効果的に入れるオープンハイハットのようなアクセント的効果をもたらすことに気が付いた。
『五分後の世界』で描写される戦闘シーンは改行がないぶん、息継ぎが許されないような息苦しさを感じる。
もちろん、それが狙いなのだろう。
刻一刻と目まぐるしく局面が移り変わる地上戦の様子と、肉体に痛みが走るようなリアルさを読者に訴えかけているのだろう。
逆に考えてみればわかりやすい。
改行だらけのスカスカなレイアウトで、あの文章をレイアウトしてみたらどうなるか?
おそらく読者は間延びした戦闘シーンと感じるのではないだろうか?
1秒ごとに局面が変化してゆく「時間内あたりに起こる出来事の情報量」を圧縮させるには、改行を無視した描写のほうが戦場のヒリヒリした感覚をダイレクトに伝えるには有効なのだと考えられる。
文字が密集した息苦しさを改行なしで畳みかけることで、読者に戦闘の息苦しさを訴えかけるのと同時に、読者が酸欠に陥らぬよう効果的に「、」を打ち、読みやすさを確保しつつも、目眩がするほどの肉体に訴えかける暴力的な感覚をも付与させているのだろう。
村上龍の「、」はハイハットである
村上龍が打つ「、」は、先述したように、まるでハイハットだ。
「、」を効果的に打つことで、演奏、いや文章に勢いとスピード感を付加することに成功している。
そう考えるのは、私は長年ベースを弾いていることと関係があるのかもしれない。
演奏をしていると、やっぱりドラムに耳がいってしまうんだよね。
ドラムの音、それもハットの音に耳を傾けてしまう癖が形成されてしまっているようだ。
だからこそ、小説という演奏の中で効果的に鳴らされる、いや、打たれる「、」に注目してしまうのかもしれない。
ハットの名手
ジャズに限らず、ドラムの名手は必ずといってよいほどオープンハイハットを使うセンスが優れている。
ハイハットの「チャッ!」の一音が効果的に挿入されるだけでも、ずいぶんと演奏が活気づいたり、スピードを感じさせることもある。
極論すれば、名手はハイハットの一打だけでグルーヴ感を生み出すことが出来るのだ。
先ほどはジャズのドラマーを引き合いに出したが、4ビート系のドラムに限らず、いやむしろ8ビートや16ビート系のタイトなリズムのほうが、ハットの使い方ひとつで、もろにドラマーの技量やセンスが浮き彫りになるのではないかと思うほどだ。
たとえば、最近私がはまっているサチモスの代表曲《ステイ・チューン》。
この曲が私がこのバンドを注目するきっかけとなったのだが、最初に私の耳を魅了したのが効果的に用いられるオープンハイハットだった。
それと、やっぱり私にとっての永遠の8ビートの名手は高橋幸宏でしょうね。
YMOが海外で行ったライヴ映像『ハラー』を見ればわかると思うが、この映像はどういうわけか嬉しいことにユキヒロ氏のドラム(次いで渡辺香津美)に焦点を当てて撮影された映像が多い。
おかげで、私はこのビデオ(当時はヴィデオで発売されていた)を手に入れた時は、とにかくアップで写されている幸弘氏のドラムを食い入るように見ていた。
予想以上に太いスティックで(しかもささくれている?)タイトなビートを叩き出すユキヒロ氏の姿を見るだけでもお宝ものの映像だが、時折、ハットをオープンにした瞬間の「♪チー」音が、非常に塩辛く、当時のYMOのエッジの立った演奏を際立たせていた。
それと、ユキヒロ氏プロデュースの立花ハジメの『テッキー君とキップルちゃん』で叩かれているドラムも、8ビートの中にシャープに立ち上がるオープンハイハットが効果的なスパイスとなっており、いまだに私がこのアルバムを愛聴しているのは、オープンハイハットが冴えた幸弘氏のドラミングにあるといっても過言ではないだろう。
読み返す楽しみ
なんだかハイハットが秀逸な音楽の話ばかりになってしまったが、村上龍の文体も「、」におけるハット効果が際立っており、気持ち良いタイミングで(あるいは気持ちの悪いタイミングで)紙上に放たれる「、」があるからこそ、私は『五分後の世界』や『愛と幻想のファシズム』を何度も読み返しているのだろうなと腑に落ちた。
もちろん村上龍は作品によってテーマが変わり、そのテーマの変化に応じて文体もかなり変えている。
よって、濃密な情報量の中に「、」を効果的に用いている作品ばかりではないが、少なくとも上記2作品はまぎれもなく、「、」の使い方が冴えた作品といえるだろう。
「、」と改行だけに注目して上記2作品を読み返すだけでも、かなり楽しめると思うよ。
記:2017/04/18